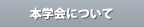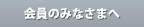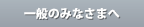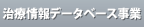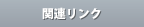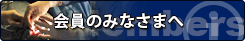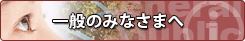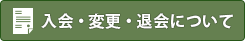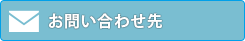日本網膜硝子体学会の会員のみなさまは、下記のサービスを会員専用サイトにて行っていただけます。会員専用サイトログイン画面からお入りください。
1. 会員情報の登録状況の確認・変更
2. 年会費納入状況の確認
※理事選挙関連書類については、会員専用サイトログイン後、「理事改選のお知らせ」より申請フォームならびに見本がダウンロード可能となります。
※ID、パスワードがご不明な場合は、ログインボタン下にあります「お忘れの方はこちら」より各々ご照会ください。
※ご勤務先やご登録住所などに変更があった場合は、会員専用サイトよりご自身でご変更いただくか、変更届を事務局補佐までFAXもしくはメール添付にてご提出ください。
『ブロルシズマブ関連ブドウ膜炎の発症予測AI開発研究』の募集について
この度、「ブロルシズマブ関連ブドウ膜炎の発症を予測する人工知能(AI)」に関する研究の募集を行います。以下の要項に従い、公募を進めます。採択された(概ね2件以内)研究チームには、総額1,500万円の研究費を提供いたします。
なお、本研究はノバルティス社の資金提供を受けておりますが、論文投稿等についての制約はございません。
ブロルシズマブ関連ブドウ膜炎の発症を予測するAIの開発
上記の研究を概ね1年以内に完成させること。
データ収集については、日本網膜硝子体学会および日本眼科AI学会が一定の協力を行います。
令和7年1月10日(金)から2月9日(日)まで
日本網膜硝子体学会会員をリーダーとするチーム
応募者の中から、日本網膜硝子体学会常務理事会にて決定します。
- 提案内容をA4用紙1枚程度にまとめた提案書
(具体的かつ時間経過を含めた内容を記載してください) - 必要経費の詳細
- 応募チームの構成
(名前、所属、およびテーマに関連する業績)
2025年2月9日締切にて公募いたしておりましたAI開発研究につきまして、多数のご応募をいただきました。
常務理事会において厳正な審査を行った結果、下記の通りに決定いたしましたので、ご報告申し上げます。
- 1位 Deep eye vision社
- 代表 高橋 英徳 先生
- 2位 京都大学
- 代表 畑 匡侑 先生
- 3位 久留米大学
- 代表 吉田 茂生 先生
- 3位 京都府立大学
- 代表 ⽥中 寛 先生
※本研究では一定の成果が求められることから、今回、1位および2位の方には研究資金として200万円、3位の方には100万円を授与いたします。
なお、研究資金を受領された方には、令和8年2月までに完成したAIを提出していただくことを義務付けます。(追加:1年後に成果を報告することを義務付けます)
その後、常務理事会にてAIの完成度を評価し、1位の方には800万円、2位の方には100万円を授与することとします。
IRDゲノム研究推進タスクフォースの募集
遺伝性網膜ジストロフィ (以下、IRD)の遺伝学的検査が2023年に保険収載されました。しかし、臨床的・遺伝学的にIRDの専門的な知識を有する眼科医の数は限られており、地域による偏りも存在します。また、臨床遺伝の専門医資格である、臨床遺伝専門医を有する眼科医の数も少ないのが現状です。
遺伝学的検査によってこれから蓄積される患者情報は、わが国のIRDの原因遺伝子の把握や新規治療法の開発において重要なものとなることが予想されます。このため、学会等の公的な組織によってこれらのデータが管理や活用されることが望ましく、日本網膜硝子体学会において研究推進タスクフォースを構築する運びになりました。
本タスクフォースでは、我が国の幅広い地域にIRDの専門家を育成し、さらに今後取得されるデータの研究への利活用を進めることを目的とします。また、遺伝学的研究の成果報告が必要とされる臨床遺伝専門医取得の支援も実施する予定です。
- IRDの専門家として診療に従事する意欲のあるもの
- 臨床遺伝専門医を取得する意欲のあるもの
- 会議の参加や研究の実施、発表準備や論文執筆に必要な時間と環境を確保できること
- 施設責任者の承諾が得られていること
- 申請時において、日本網膜硝子体学会員であること
- 年齢や性別は問わない
- 採用予定人数:6-8名
- 予定期間:令和7年3月1日(土)~令和9年3月31日(月)
- Web会議ツールを用いた症例検討や研究プロジェクトの進捗報告を定期的に実施
- IRD臨床(画像診断学、電気生理学、遺伝学)の講義
- 表現型の解析やゲノムデータを含むバイオインフォマティクス講習
- 対面での意見交換・研究成果報告会(年1回を予定、費用補助あり)
< 予定している研究内容 >
- レジストリやパネル検査で蓄積されるゲノム・臨床データの活用 (表現型-遺伝型の解析)
- パネル検査に関する検討
- 非典型的な臨床所見を呈するIRDの検討
- 機械学習を用いた新しい研究ストラテジーの開発
下記に記載の書類を事務局宛にメールで提出すること。
< 提出書類 >
- 申請書(様式1)
- 推薦書(様式2)
応募受付締切
2025年1月31日(金)必着
- 書類選考(2月中旬までに結果は通知予定)
- 面接(web面接、2月末から3月中に採用の可否をそれぞれに連絡予定)
※選考基準
地域的な偏りや女性からの応募などについては、ダイバーシティ推進の観点から考慮する。
IRD専門家が少ない地域からの応募を重要視する。
藤波 芳(独立行政法人国立病院機構東京医療センター 臨床研究センター 視覚研究部視覚生理学研究室)
大石 明生(長崎大学大学院医歯薬学研究科 眼科・視覚科学教室)
秋山 雅人(九州大学大学院医学研究院 眼病態イメージング講座)
※30-40代のアドバイザー数名が本タスクフォースに参加し参加者のサポートを行う予定。
E-mail: vitreoretina@jtbcom.co.jp
2025年1月31日締切にて公募いたしておりました遺伝性網膜ジストロフィの研究ユニットにつきまして、多数のご応募をいただきました。
オーガナイザーにより厳正な審査を行った結果、下記の通り7名の参加者を決定いたしました。
- 淺野 祥太郎
- (東京大)
- 江戸 彩加
- (広島大)
- 尾崎 篤汰
- (三重大)
- 我謝 朱莉
- (琉球大)
- コンソルボ 上田 朋子
- (富山大)
- 中島 勇魚
- (高知大)
- 村上 智哉
- (筑波大)
また、本タスクフォースでは、以下の5名にスーパーバイザーとして参加いただくことになりました。
- 秋葉 龍太朗
- (千葉大)
- 小柳 俊人
- (成育医療センター/九州大)
- 鳥居 薫子
- (浜松医大)
- 沼 尚吾
- (京都大)
- 平形 寿彬
- (順天堂大)
若手を中心としたタスクフォースですが、大学医局を超えた連携により遺伝性網膜ジストロフィ研究の活性化や診療格差の解消に繋がる人材育成に努めてまいります。
- 藤波 芳
- (独立行政法人国立病院機構東京医療センター)
- 大石 明生
- (長崎大学大学院医歯薬学研究科)
- 秋山 雅人
- (九州大学大学院医学研究院)
『データサイエンス時代の次世代研究者育成プログラム』募集のご案内
近年、基礎・臨床研究のいずれにおいても、良質な成果を得るために高度なデータ解析が必要となり、ビッグデータ解析技術を有する人材の需要は高まる一方です。日本の眼科の国際的プレゼンス向上のためには、データサイエンスを理解し国内のデータリソースを利活用できる研究者を育成することが急務です。本プロジェクトでは、本邦の有望な若手人材を発掘し、ビッグデータ解析で実績を有する眼科医師(九州大学 秋山雅人、京都大学 三宅正裕)がデータ解析を軸とした若手育成に取り組み、網膜硝子体領域の研究活性化と眼科分野のデータサイエンスを牽引する次世代リーダーの育成を目指します。
- 35才未満(令和5年3月31日時点)
- データ解析やその習得に必要な時間を確保できるもの。
- 大学院生の参加も可能だが、指導者の承諾を事前に得ること。
- 申請時において、日本網膜硝子体学会員であること。
- 採用予定人数:4名
- 予定期間:令和5年4月1日(土)~令和7年3月31日(月)
- 下記実施内容について、月に1–2回程度とグループミーティングを行う。
- 年に1–2度、対面でのワークショップも実施予定。
- 外部研究者によるデータサイエンスや次世代医療に関する講義を予定。
< 実施内容 >
- データ活用のための知識や技術の習得(RやPythonなどのプログラミングを含む)
- プレゼンテーション技術や研究資金獲得など、Principal Investigatorに必要とされる能力の習得(公的研究費応募時には、POが支援する)
- 網膜硝子体学会やJapan Ocular Imaging Registry(JOIR)などにより構築されたデータベース/リソースを用いた解析の実践(AI解析を含む)
下記に記載の書類を事務局宛に提出すること。
< 提出書類 >
- 申請書(様式1)
- 推薦書(様式2)
応募受付締切
2023年1月31日(火)必着
- 書類選考(2月下旬に結果は通知予定)
- 面接(web面接、3月中に採用の可否をそれぞれに連絡予定)
※選考基準
これまでの業績は重視せず、将来的展望や眼科の現状に対する問題意識など、これからの日本の眼科に貢献可能な素質を重視して選考する。また、地方在住者や女性からの応募などについては、ダイバーシティ推進の観点から考慮する。
秋山 雅人(九州大学大学院医学研究院 眼病態イメージング講座 講師)
三宅 正裕(京都大学大学院医学研究科 眼科学 特定講師)
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号 大阪堂島浜タワー5階
株式会社JTBコミュニケーションデザイン コンベンション第二事業局内
日本網膜硝子体学会 事務局補佐 宛
※申請にあたりご不明な点がございましたら、事務局メール(vitreoretina@jtbcom.co.jp)にお問合せください。
「日本網膜硝子体学会 基礎研究助成プログラム2022」
募集のご案内
平素は日本網膜硝子体学会の活動にご理解とご協力をいただき誠に有難うございます。
さて、日本網膜硝子体学会では、「日本網膜硝子体学会 基礎研究助成プログラム」を設け、公募をさせていただく事になりました。
応募される先生は下記要領をご覧の上、「申請書」「推薦状」をダウンロードしていただき、必要書類と共に事務局補佐にご郵送ください。
日本網膜硝子体学会 基礎研究助成プログラムは、眼科領域の新しい診断/治療につながる基礎的研究の発展に寄与するため、新たに設立された助成プログラムです。
日本国内の大学・大学院、研究機関等に所属する若手研究者を対象として、優れた研究計画に対して助成を行うことにより、わが国の眼科医学の一層の進歩に寄与することを目的としております。
- 網膜硝子体に関する研究であること。
- 申請時において、日本網膜硝子体学会員であること。
- 日本国内の大学・大学院、あるいはそれと同等の研究機関に所属する若手研究者(原則として40歳以下)であること。
- 過去5年間に本助成を受けたことがないこと。
- 募集時に当学会の他の助成を受けていないこと。
- 1施設から1件のみの応募とし、施設責任者の推薦状を必要とする。
- 助成金総額 600万円 - 1件200万円以内
- 助成件数 3件
- 使途:本研究に必要な物品等の購入、および経費、謝礼、旅費等にも使用可能とする。
下記に記載の書類を事務局宛に郵送すること。
<提出書類>
- 申請書(様式1)
- 推薦状(様式2)
- 代表論文の別刷りコピー6部 3編以内
※3については電子ファイルでの提出も可とする。電子ファイルをメール添付にて事務局メールへお送りください。
- 当助成プログラムの審査委員会(日本網膜硝子体学会理事を中心とした5名)において審査を行い、理事会承認を経て最終決定とする。採否は2022年10月末迄に申請者宛に電子メールにて通知する。
- 研究助成金は助成決定者に金融機関振込により交付する。
- 助成決定者は2023年10月時点で、研究成果報告書を提出すること。
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目1番27号 大阪堂島浜タワー5階
株式会社JTBコミュニケーションデザイン コンベンション第二事業局内
日本網膜硝子体学会 事務局補佐 宛
※申請にあたりご不明な点がございましたら、事務局メール(vitreoretina@jtbcom.co.jp)にお問合せください。
2022年9月30日締切にて公募いたしておりました基礎研究助成プログラムにつきまして、多数の申請をいただきました。
審査委員会において厳正な審査を行った結果、下記3名の先生を採択することと決定いたしましたので、ご報告申し上げます。
「網膜色素変性におけるEYS非翻訳領域の原因解明」
「ヒトiPS細胞由来網膜オルガノイドとマイクログリアの新規共培養系を用いた難治性網膜疾患におけるマイクログリアの機能解析」
「自然免疫記憶と加齢黄斑変性」
2021年11月30日締切にて公募いたしておりました基礎研究助成プログラムにつきまして、多数の申請をいただきました。
審査委員会において厳正な審査を行った結果、下記4名の先生を採択することと決定いたしましたので、ご報告申し上げます。
「未熟児網膜症に対する新規治療ターゲットの模索」
「血管の恒常性制御に基づく、網膜疾患の病態解明と新規治療開発」
「眼科診断に特化した人工知能モデルの探索」
「遺伝子改変マウスを用いた糖尿病網膜症病態における FABP4 (fatty acid-binding protein 4)の役割の検討」
2021年3月10日締切にて公募いたしておりました基礎研究助成プログラムにつきまして、多数の申請をいただきました。
審査委員会において厳正な審査を行った結果、下記5名の先生を採択することと決定いたしましたので、ご報告申し上げます。
「3次元培養を用いた強度近視の疾患モデルの確立」
「RPEにおけるメカノホメオスターシス破綻を標的とした革新的新規nAMD治療薬の開発」
「加齢黄斑変性モデル動物を用いた網脈絡膜の網羅的脂質代謝解析」
「老化細胞を脱分化・ダイレクトリプログラミングさせるメカニズムの解明」
「網膜硝子体疾患の病態解明に向けたオールジャパンでの眼科ゲノム研究基盤構築」